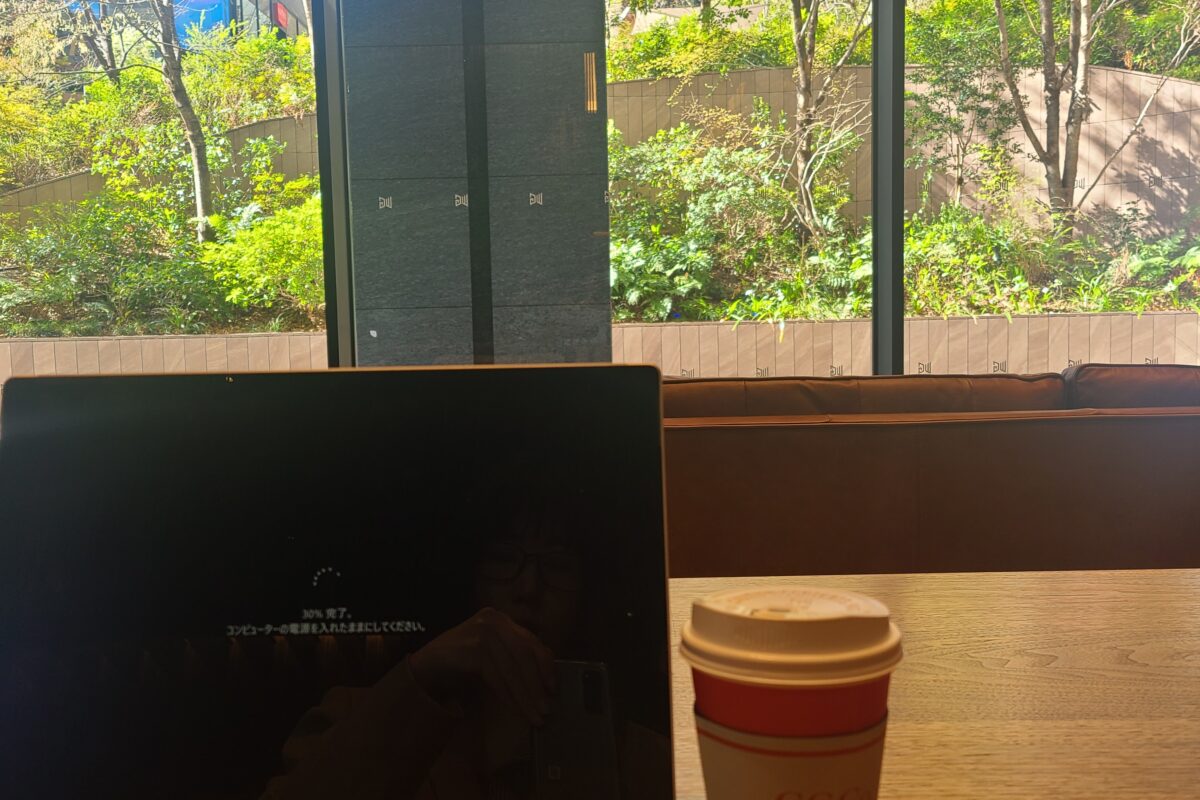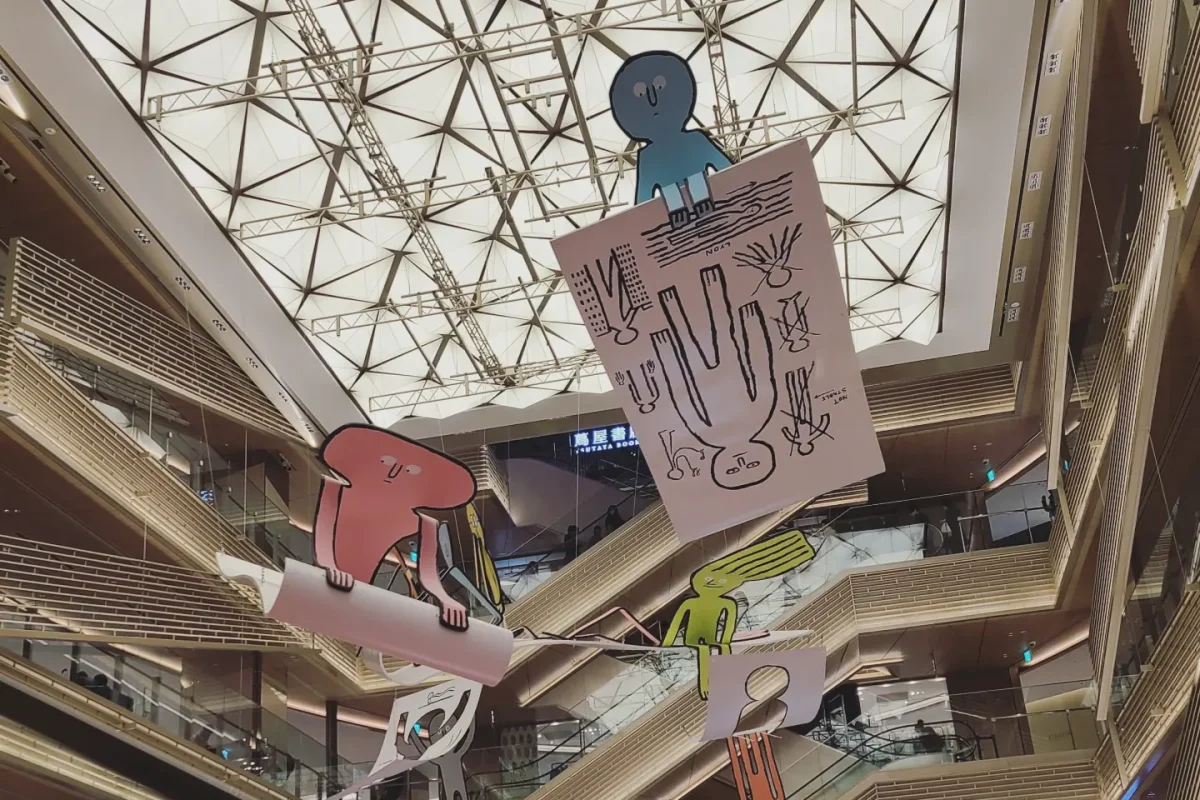2023年4月28日(金)日経MJ
「飲食店、うまい値上げの方法は?」
コンサルタント勝田耕司氏
居心地にお金かける、というところが印象的だった。
引用
「コストアップが止まりません。バリューを高めるにはどこにお金をかけて、どこを削りますか。
『『見えないところ』にこそお金をかけるべきです。つまり接客を含めた居心地です。人への投資は必須。従業員にやさしく、というのは大切ですが、気をつけたいのはコロナ禍時代の『習慣』を引きずること。
先日、閉店の30分以上前に掃除を始めた店がありました。お客さまは食事中です。従業員に早く帰ってもらうためでしょうが、おもねってばかりいると、お店の空気は変わります。インフレ下の今、消費者の外食の頻度は落ちます。一旦期待を裏切れば、食事は家でいい、となってしまいます』
とのこと。
居心地かぁと納得。これは目に見えないし難しい。一朝一夕ではできないし、従業員満足度も影響してくる。従業員満足度が上がれば、顧客満足度も上がるというのがセオリーだ。
居心地とは少しずれるが、「居場所」について興味深い本があった。
村上靖彦さんの
「交わらないリズム
~出会いとすれ違いの現象学」
ちょっと難しくて、全部読めてないが、印象的なところ、以下のようにある。
引用
「居場所とは人が自由に『来る』ことができ、『居る』ことができ、『去る』ことができる場所である。
さらに言うと、『何もせずに』いることができる場所であり、一人で過ごしていたとしても孤独ではない場所である。なぜ一人でいても孤独ではないかというと誰かがそこでその人を気にかけ、見守り、放っておいてくれるという感覚があるからである。
逆説的だが、居場所とは人と出会える場所であり、かつ一人になれる場所のことだ。」
という。
これが居場所といわれて納得できる人も多いのではないだろうか。こういう居場所が減ってきたのが近代であるともいえる。
本書では、地域のデイケアや就労移行支援作業所などの研究からこの「居場所」が導かれており、飲食店などビジネスとはずれるけれど、ヒントにもなる。
人が「居る」ことができる場所というのは尊いと感じる。そういう場所が希少だということかもしれない。